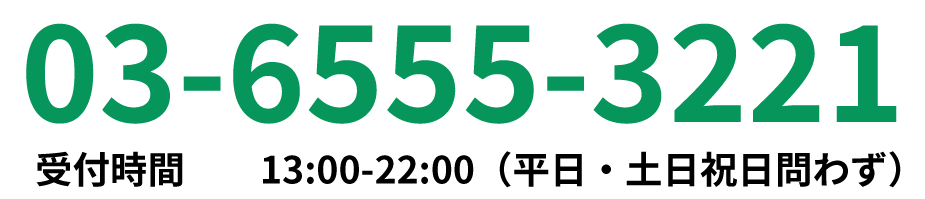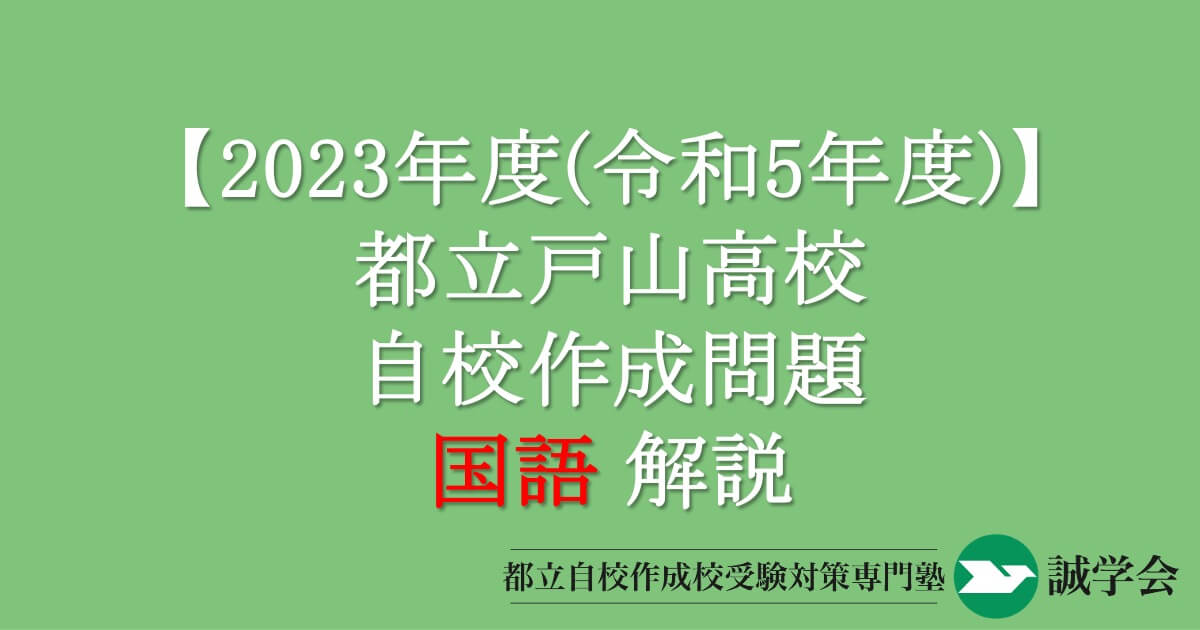こんにちは!都立自校作成校受験対策専門塾・誠学会の諏訪孝明です。
この記事では、2023年2月に行われた都立戸山高校の自校作成問題の国語の大問3物語文(小説)・大問4説明文(評論文)・大問5鑑賞文(古典を題材にした説明文)の問題を解説します。
自校作成校受験生のうち、
・国語で安定して高得点をとるための読み方・解き方を知りたい
・物語文が苦手
・難解なテーマの文章を読解するのが苦手・過去問演習の後、自分の読み方
・都立高校入試に独特の形式である鑑賞文に苦戦している
・過去問演習の後、自分の読み方・解き方や理解・解釈が合っているのかどうかを確認したい
といった方におススメです。
なお、今回の解説をより理解するために国語を解くときに気を付けてほしいことをこちらにまとめております。
今回の解説に先んじて読んでおいていただくと理解が深まります。
是非読んでみてください。
また、一度自力で本文を読み設問を解いてから読むことを強くお勧めします。
では、解説をはじめます。
目次
- 1 大問3本文
- 2 大問3設問
- 3 大問4本文
- 4 大問4設問
- 5 大問5本文
- 5.1 其角
- 5.2 歌枕
- 5.3 西行
- 5.4 ~はできない
- 5.5 芭蕉
- 5.6 から
- 5.7 また
- 5.8 から
- 5.9 めずらしい⇔ふつう/かわりに
- 5.10 頭韻を「ウ」で揃える
- 5.11 ~が多い。しかし…
- 5.12 ~してしまう
- 5.13 ~に見えるが、…~であろうと思う
- 5.14 こそ
- 5.15 最も
- 5.16 から
- 5.17 AよりもB
- 5.18 ~と思われる
- 5.19 ~が必要である
- 5.20 ~であろう
- 5.21 比喩的表現
- 5.22 ことさらに重要
- 5.23 ~のである
- 5.24 一層強調される/一層強調され
- 5.25 ~であろう/~と思われる/~に思われる
- 5.26 反省されている
- 5.27 つまりは/~のである
- 5.28 ~らしい
- 5.29 ~だろう/~であろう
- 5.30 造化
- 6 大問5設問
- 7 都立戸山高校に合格するなら自校作成専門対策塾 誠学会
大問3本文
前文があるので、状況の把握が可能となっています。
夫・妻とおじちゃん・おばちゃんという2組の夫婦が登場するようです。
この2組の夫婦は大家さんと住人という関係性でありながら食事会をしています。
皆さんのなかで賃貸マンション暮らしの人へ質問ですが、大家さんと食事会をしたことはありますか?
おそらく、無いと思います。
今回の夫婦は、通常はしない「大家さんとの食事会」をしています。
関係がとても良好だと判断できます。
それを踏まえてみていきましょう。
第1段落
いちばん好きな時間
最上級表現はとても重要です。
春先の朝、布団のなかで過ごす目覚めと眠りの狭間にいる時間が好きなようです。
第2段落
冬でもあたたかかった
冬は寒い季節ですが、そんな季節でも暖かかったという意外性が用意されています。
ですので、ここは要注目です。
第3段落
二階は寒くないでしょ
おじちゃんも同じ認識(寒くない=あたたかい)のようです。
第4段落
しかし
対比構造を示します。
「寒い」⇔「あったかい」の対比です。
から
因果関係を示します。
一階の熱が上に上がる⇒二階が暖かい
という因果関係です。
くらべられない
反復されている表現です。
比べる=対比構造ですから、とても重要です。
そして、「比べられない」というのは「絶対的な存在だ」という意味です。
他と比べられないくらい特別な存在だということを意味します。
第5段落
暮らしてみないとわからない/暮らしはじめて…気がつく
同じような意味の言葉が言い換えられています。
こういうフレーズも要注目です。
これまで同様、「あたたかさ」に関する記述です。
第6段落
そのとき
新しい家で暮らしはじめて、「あっ、今までの家は暖かかったんだな」と気づくときのことです。
いちばん好きな時間
第1段落で言及のあった時間のことですね。
あの家のあたたかさ
「一階の熱」による暖かさだけでなく、おじちゃん・おばちゃん夫婦の体温(ぬくもり)が構成要素であることへの言及です。
2組の夫婦の心理的な距離が近いことが分かりますね。
第7段落
妻は…暖気になって/ような
人間は暖気になることはできません。
ですので、ここは「比喩表現」であることが分かります。
いちばん好きな時間
第1段落で出てきたフレーズの再登場です。
第8段落
驚いた
登場人物の心情なので重要です。
ここで驚いたのは主人公の「妻」ではなく「夫」です。
驚いたきっかけは書いてありますが、なぜそれが驚きにつながったのかは書いてありません。
おばちゃんの話はあまり聞こえず⇔ちゃんと聞こえる
注に書いてあることですが、おじちゃんは年齢のためか耳が遠くなっているようです。
にもかかわらず、「好きな時間は?」という問いが聞こえたようです。
特別な問いであったようです。
困った
おじちゃんが困っています。
返答に困っているようです。
それは、続く会話の場面の「特にないよ」からわかります。
第9段落
そんなことないでしょう
「旅行にはもうなかなか行けない」に対する回答です。
ここでは、
去年やその前年にも行っている⇒なかなか行けていないわけではない
という流れです。
驚き/関心
妻のおじちゃんへの感情を示します。
前述のとおり、登場人物の心情は重要です。
重要な事柄は設問の解答根拠になりやすいです。
第10段落
いちばん好き
最上級表現は重要です。
おじちゃんは仕事がいちばん好きなようです。
第11段落
目くばせ×2
夫婦の連帯感・仲の良さを示していると考えられます。
第12段落
まじめだけでつまんない人
おばちゃんのおじちゃんに対する人物評価を示しています。
「つまんない」はマイナスの評価ですが、ここでは「笑い」「顔を向けた」とあるのでプラスの評価をしている雰囲気があります。
「遊びは全然しない」「仕事だけ」な夫にプラスの評価をしていることが分かります。
第13段落
照れ/よろこんでいる
おじちゃんのおばちゃんに対する反応です。
プラスの評価に対し、プラスの感情で応えているのが分かります。
第14段落
誇り
おばちゃんのおじちゃんに対するプラスの評価・感情がはっきりとわかります。
「本当に一生懸命」「顔を向ける」「うん」といったところからもプラスの評価やおじちゃん・おばちゃん夫婦の仲の良さや絆の強さが読み取れます。
第15段落
柔らかな表情/感謝/よかった
おばちゃんのおじちゃんに対するプラスの評価・感情がここでも伝わってきます。
ふたりの声
おばちゃんだけでなく、おじちゃんも仕事に誇りを持ち、「仕事を一生懸命頑張ってきてよかった」と思っていることが読み取れます。
大問3設問
問1
問1を解く上で重要になるのは
・暮らしてみないとわからない⇒現時点で何かしらの評価をしているわけではない
です。
それを踏まえると、
ア:新生活に胸の高鳴りを感じる⇒×
イ:「あたたかさは得られないだろう」⇒×
エ:「これからの暮らしに楽しみを感じる」⇒×
となるので、消去法的にウとなります。
問2
問2は
・暖気になる
・我に返る
というところから、これが「比喩表現」であり本当の話ではないということです。
ア:「寝室に行きたい」⇒×
イ:「空想の世界」⇒〇
ウ:「早く席を外したい」⇒×
エ:「話題探しに夢中」⇒×
問3
「特にない」⇒なんと答えてよいかよくわからない(それは、仕事一筋の人生だったから。)
がポイントです。
ア:「うしろめたさ」⇒×
イ:「嫌がっている」⇒×
ウ:「味気なく思っている」⇒×(ラストに書いてある通り、誇りに思っています。最後まで読んでから選べば、この選択肢を選ぶことはありません)
エ:「適当な答えが思いつかず」⇒〇
問4
「そんなことないでしょう」と言ったときの妻の気持ちを答える問題です。
ここでのポイントは
・おじちゃんは旅行には行っている
・驚きがある⇒高齢なのに頻繁に旅行に行っているから
・感心している⇒高齢なのに気が若く元気だから
となります。
これらを60字以内でまとめればOKです。
例
高齢なのに頻繁に旅行に行っていることに対する驚きと、気が若くて元気であることに対する感心を伝えたいという気持ち。(56字)
問5
「ふたりの声」:しゃべっているおばちゃんだけでなく、おじちゃんも同じ想いであることや2人の絆の強さを感じる表現です。(詳しくは本文解説を終盤を参照してください。)
ア:「両者の信頼関係」⇒〇
イ:「話をするのはおばちゃんだけの特権」⇒×
ウ:「表情を変え続けていく」⇒×
エ:「取り合おうとしなかった」⇒×
問6
ア:「隔たり」⇒登場人物たちの心理的な距離は近いです⇒×
イ:「煮え切らない態度」⇒×
ウ:「第三者の視点」「視点の移動」⇒〇
エ:「話題の転換点」⇒×
大問4本文
「大正時代に書かれたもの」とわざわざ紹介されているので、時代背景が分からないと誤読する可能性がある文章であると推測できます。
第1段落
とは
「とは」は、用語の意味や用法を定義するときに使われる表現です。
ここでは、「骨董趣味」という語の意味が紹介されているのでそれがキーワードであると判断できます。
骨董趣味=古美術品の鑑賞
と定義されています。
不純⇔純粋
分かりやすい対義語のペアとなっています。
骨董趣味⇔芸術的の趣味
という対比構造が分かります。
「区別」という語からも対比構造があることが分かります。
あるいは
物事を列挙するときに使われる表現です。
ここでは、骨董趣味について
・「時」の手が加わる
・時代の匂が生じる
・歴史的連想も加わる
・昔の所蔵者に関する連想
・古いので現在稀有
・愛着の念
といったものが価値の源泉であることが分かります。
「骨董趣味」というキーワードを説明しているので、ある程度注意して読まなければなりません。
不純な趣味
先ほどあった「不純」⇔「純粋」の対比に関わる語ですので、キーワードの1つです。
ここからは、さらに注意して読みましょう。
不純な趣味=人に誇る(=自慢する)
とされています。
第2段落
科学
高校受験現代文において「科学」という言葉が出てきたらキーワードになることがほとんどだと考えてください。
高校は義務教育ではありません。
高等教育です。
生活にも直接深く関わる義務教育の内容に加えて、さらに「科学」を勉強したい人が集まる場所です。
なので、「科学」は重要なワードとなります。
「新しく発見された」⇔「旧くから知られている」
こちらもわかりやすい対義語です。
対比構造なので、重要です。
べきものではない
筆者の主張があることを示す文末です。
ここでは、「古いか新しいかは重要ではない」という主張がされています。
~であるべきように見える。しかし…
「一般論+逆接+主張」の形をとっています。
ここでは、
「科学の世界でも骨董趣味は常に流行している」という主張です。
第3段落
人間未生以前から
「古くから」ということです。
骨董趣味は「古いもの」に対して感じる愛着ですのでこのワードに注目できると良いですね。
このくらい…なものはない
最上級表現は重要です。
また、ここでは「古さ」の最上級ですのでそこからも重要であると判断できます。
類する点がある
科学者の欲望≒骨董趣味
と主張しています。
対比(⇔)が重要であるのと同様、「=」や「≒」といった関係性も重要です。
AではなくB
・A⇔Bの対比構造があること
・AよりもBのほうが文脈上重要であること
が分かります。
芸術家の創作的欲望
こちらは骨董趣味と対比される「純粋な芸術的の趣味」のことを指すと判断できます。
今回のメインテーマとは離れています。
科学的骨董趣味
ここまでの対比構造が分からなくても、この語をみれば筆者が「科学≒骨董趣味」という図式をつくっていることがダイレクトに理解できます。
第4段落
種々の階級がある/多種多様である
言い換え表現は重要であることが多いです。
しかし、ここでは
区別は別問題/本文の範囲外
と述べているので重要ではないと判断できます。
二つ/二種/対照
ここから対比構造に注目して読むべきパートが続くと分かります。
第5段落
歴史×2、古い
骨董趣味に関する説明で用いられていたワードです。
骨董家、骨董趣味×2
今回のメインキーワードです。
科学における骨董趣味の1つ目は、「科学の歴史」を愛することのようです。
第6段落
次に
1つ目の紹介が終わり、2つ目の紹介に移ることの目印です。
骨董趣味/骨董的傾向
今回の文章のキーワードです。
これが骨董的傾向を帯びる
「これ」という指示後の具体化が重要です。
今回は、「先人の研究を引用し批評すること」です。
これが科学における骨董趣味の2つ目であるようです。
第7段落
正反対の極端
対比構造を示す語です。
歴史
骨董趣味の人が大事にするものです。
全く無意味
骨董趣味とは別の価値観を持った人たちのことを紹介する流れになっていることが分かります。
最新の知識
「古さ」とは対極にあります。
ここまで読むと、「正反対の極端」が何を指しているのかが分かります。
「古いものは何物でも無価値」⇔「新しきものは無差別に尊重する」
分かりやすい対比構造です。
骨董趣味=古いものが好き
に対して、
新しいものが好き
という価値観を紹介しているようです。
第8段落
日進月歩の新知識
骨董趣味とは対極にあります。
歴史的の詮索までに手の届かぬ
こちらも骨董趣味ではありえない話です。
第9段落
科学上の骨董趣味
この文章の最重要キーワードです。
軽視すべきものではない
重要である、ということです。
例えば
具体例を提示することを示す語です。
科学において骨董趣味が重要であることを示す具体例が続くようです。
このような類例
「このような」とあることから、ここで具体例が終わりその共通点を紹介するパートに移ることが分かります。
「新しい芸術」⇔「古い芸術」
分かりやすい対比構造です。
ここでは、次の
「新しい科学」⇔「昔の研究」
につながっています。
新しき衝動
古き考の余燼から産まれ出る
これらも、「新しい」と「古い」の関係性を示しています。
第10段落
現今大戦
大正時代の文章ですから、これが第一次世界大戦を指しているとわかります。
これがあるので、わざわざ「大正時代に書かれた文章である」と示されていたのでしょう。
科学は応用の方面に
科学のジャンルにおける「応用」とは、私たちの生活に役立つモノや技術を開発するという意味です。
成果が目に見えて分かりやすいため世間の人々から称賛されやすく、金儲けにもつながりやすいため企業からの協賛も得やすいです。
したがって、科学者も応用研究に力を入れてしまいがちです。
しかしながら、基礎研究も重要です。
基礎研究とは、「知的好奇心に基づいて何かを明らかにしようとする」営みのことです。
何の役に立つかは分かりません。
その一方で、基礎研究の成果の積み重ねが応用研究に文字通り「応用」されて新しいモノや技術が生み出されていきます。
このことから、
応用研究だけではなく、基礎研究の重要性をしっかりと理解し、それを国も企業もサポートしていかなければならない
と主張する文章が出題されることは非常に多いです。(今回もそういった流れになっています。)
ですので、ここで書いたことはしっかりと覚えておきましょう。
説明文を読むのに必要な「常識」です。
骨董趣味
今回の文章のキーワードです。
功利
ここでは経済的な利益のことであり、上述の通り応用研究と相性が良いです。
純知識欲に基づく科学的研究
基礎研究のことです。
あってはならぬ/思う
筆者の主張があることを示す文末です。
ここでは、
「応用研究ばかり重視せず、基礎研究の重要性もしっかりと理解せよ」
という主張がなされています。
第11段落
温故知新
昔のことから新しい知識や見解を得ることです。
まさにこの文章が示している内容です。
~のである
筆者の主張があることを示す文末です。
ここでは、
「科学においても昔のことから新しい知識や見解が得られることがあるはずだ」
というものです。
大問4設問
問1
第1段落の内容から、
・骨董趣味:古美術品の鑑賞
・不純な趣味:人に自慢すること
となります。
これを満たす選択肢を選びましょう。
ア
化石:美術品ではありません
イ
多くの人の公開する:自慢していません
ウ
即座に手に入れる:自慢していません
エ
平安時代の能筆家の書:古美術品です
ひけらかす:自慢しています
これが正解です。
問2
「常に新鮮なるべきもの」とは、骨董趣味とは正反対の嗜好です。
というわけで、「これ(骨董趣味)と正反対の極端にある」とある第7段落の内容をまとめると正解できそうだと判断できます。
傍線部2は第2段落にあります。
この問題の答えが第7段落の内容となるのは、
「傍線部の周辺から答えになりそうな箇所を探して答える」
というやり方では絶対に正解できませんね。
皆さんのなかでそういうやり方しかできない人がいたら、文章の全体像を論理的に読解する読み方を習得できるようにしてください。
今回は、
「古いものは何でも無価値」「新しいものは何でも尊重する」
という表現を入れておけば得点できると考えて良いです。
問3
ここでの「科学者の要求」とは、骨董趣味とは対比される「芸術的の趣味」に類するものです。
したがって、骨董趣味が重視する「古いもの」「歴史」「先人の研究」といったものは重視しないはずです。
ア
原初から存在する⇒×
イ
骨董趣味が重視しそうなものが書いてありません⇒〇
ウ
定説を念入りに検証⇒×
エ
「世の中を驚かせたい」
これは、この文章のどこにも書いてありません。
書いていないので、×です。
問4
「科学上の骨董趣味」が軽視されてしまう理由です。
これは「応用研究の重視」つまり「すぐに役に立つことの重視」です。
ア
個人的な満足感を満たそうとしている⇒×
イ
生活の向上という研究の目的⇒〇
ウ
激しい時代の流れから目を背けようとしている⇒×
エ
先行研究の価値を証明することを目的⇒△
内容として間違ってはいませんが、ここでのメイントピックではありません。
問5
「このような類例」とは、
昔の研究の成果を参考にして新しい科学的な発見がなされる例を指しています。
ア
思いつき⇒×
イ
精神的支柱⇒×
ウ
途方もない夢⇒×
エ
飽くなき探求⇒〇
問6
応用研究だけでなく基礎研究のこともしっかり重視しよう、という主張です。
筆者は傍線部直後で「直接の応用には限界があり、予想外の応用が大事だ」と述べています。
ア
他者の様々な意見を受容する態度⇒×
イ
平和の実現を求めて⇒×
ウ
思いがけない発想⇒〇
エ
唯一の手段⇒×
問7
いわゆる200字作文です。
「温故知新」が役に立つことについて述べるよう求められています。
これには、昔はできていたが、今は上手くできていない事柄がぴったりです。
したがって、私が推奨する内容は
・自然との共生
・大量生産・大量消費とは無縁の暮らし
すなわち
・持続可能性の追求
・環境への配慮
などとなります。
200字作文は学校が解答例を公開してくれていますので、それを参考にしながら書くと良いです。
得点力アップのためには、書いた200字作文を都度添削してくれる塾やサービスを利用しましょう。
大問5本文
其角
この人自体は「有名人」ではないですが、松尾芭蕉の門人(≒弟子)です。
有名人の関係者なので、この人が文章のなかでキーパーソンになる可能性があると考えます。
(実際には、この文章では其角はあまり重要ではありません。)
歌枕
古くから和歌で詠まれることの多いスポットです。
過去の人が詠んだ歌を基にした歌があり、それを知識として知らないと歌の良さが分からないことがあります。
和歌を詠むのも楽しむのも知識・教養が必要になるということですね。
西行
平安時代末~鎌倉時代の歌人です。
都立大問5・鑑賞文の界隈では「有名人」です。
全国各地を旅してたくさんの歌を詠みました。
~はできない
筆者の主張があることを示す文末です。
「松尾芭蕉と西行とのゆかりが重要である」という主張です。
芭蕉
超がつくほどの有名人です。
この人も旅をして歌を詠んだので西行との類似性がありますね。
から
因果関係を示す表現です。
原因:西行の行動から芭蕉が思いつき(着想)を得て歌を詠んだ
結果:芭蕉と西行にはゆかりがあるといえる。
また
から
何かを追加する表現です。
ここでは、西行と芭蕉のゆかりを示す因果関係の追加です。
西行の歌が芭蕉の句の「潮の花」というフレーズに影響を与えている
ということです。
めずらしい⇔ふつう/かわりに
分かりやすい対義語のペアです。
こういうときに対比構造を意識するようにしてください。
「潮の花」 ⇔「シオバナ」
めずらしい ふつう
AのかわりにBというのも、AとBの対比構造を示します。
頭韻を「ウ」で揃える
五・七・五・七・七のそれぞれのフレーズの頭文字を「ウ」で揃えるということです。
和歌の技法については事前知識を持っておくと大問5・鑑賞文が詠みやすくなります。
~が多い。しかし…
一般論+逆接+主張
の形をとっています。
今回の主張は
「波の花」は波頭一般をいうものだ
というものです。
~してしまう
マイナスのニュアンスをもたせるときに用いられます。
そのとき、「AはBじゃない」という主張がなされます。
ここでは、
「潮の花」≠「波の花」(波頭一般)
という主張です。
~に見えるが、…~であろうと思う
譲歩+逆接+主張
の形です。
今回の主張は
「潮の花」=「満ちて来る潮の花」
です。
こそ
最も
どちらも強調表現です。
また、
から
という因果関係と
AよりもB
という対比構造を
示す表現があり、
~と思われる
という筆者の主張があることを示す文末があることから
このあたりに書いてあることが文章全体を理解するうえでとても重要であることが分かります。
ここでは、
芭蕉の句のなかの「潮の花」とは、「潮が満ちて来るタイミングでのみ見られる潮の花」である
という主張をしています。
~が必要である
筆者の主張があることを示す文末です。
が、今回は
多少のまわり道が必要である
ということしか言っていないのであまり重要ではありません。
~であろう
こちらも筆者の主張があることを示す文末です。
今回は
1つの微妙な意味=「潮の花」をうたがってしまうような気持ちを持ちたくない
といったような内容になっています。
「潮の花」は今回の文章のメインテーマですので、重要な箇所であると判断できます。
比喩的表現
比喩とは、あるものを他のあるものに例えて説明する表現方法です。
一種の「ウソ」ということになります。
今回でいえば、「潮の花」と言っていますがそこに花が咲いているわけではありません。
ことさらに重要
「重要」というだけでも重要ですが、それをさらに強調しているのでここが特に重要な箇所であることが分かります。
内容は、
「花」という言葉の、和歌における重要性(春を想起させる)
というものになっています。
~のである
筆者の主張があることを示す文末です。
ここでは、
「反省されている」という主張です。
「反省」というと、何か悪いことをしたように思えるかもしれませんがそうではありません。
「反省」は「もう一度しっかり考えてみる」といった意味です。
一層強調される/一層強調され
ここでは強調表現と、
~であろう/~と思われる/~に思われる
という筆者の主張があることを示す文末が多用されています。
ここも重要な箇所になるようです。
ここの内容は
「潮の花」を疑ってはならない
という既に紹介した内容を繰り返しています。
反省されている
傍線部4で使われていた言葉の反復です。
同じ言葉の繰り返しは見逃さず注目できるようにしましょう。
それが傍線部の言葉であればなおさらです。
つまりは/~のである
要点や筆者の主張があることがわかります。
ここでは、
(「潮の花」という比喩表現を通して)言語のもつ象徴機能とその所以を明確に意識している
という主張になります。
~らしい
「潮の花」が本当は花ではないのに花に見えるのは人為を超えたところにあるものの仕業(=神仏の威徳)である
ということを伝えています。
~だろう/~であろう
このあたりで「神仏の威徳」というフレーズが繰り返されているので、これをキーワード認定します。
造化
注によると、「人為を超えたもの」という意味です。
つまり、「神仏の威徳」です。
「神仏の威徳」が再度言い換えられているということは、キーワード認定して間違いないとわかります。
ここまで何度も言われていると、「設問で使いそうだな」と判断できるわけです。
大問5設問
問1
西行とのゆかりは2つ示されています。
①西行の行動から芭蕉が何かを思いついた
②西行の歌が芭蕉の句の「潮の花」というフレーズに関わっている
この2つです。
これらを両方とも説明できている選択肢を選びましょう。
ア
どちらも書いてあります。
イ
「旅に出たいと考えた」⇒×
ウ
「西行が歌を詠んだ」⇒×
エ
其角が見出した⇒×
問2
頭韻を「ウ」で揃える
=五・七・五・七・七のそれぞれのフレーズの頭文字を「ウ」で揃える
ということの意味が分かっているかどうかです。
エ
エのみ、すべて「よ」で始まっていて頭韻が「ヨ」で揃っています。
問3
「潮の花」⇔「波の花」という対比における筆者の考えを尋ねる質問です。
筆者の結論は
「潮の花」とは、(一般的な波頭ではなく)「潮が満ちて来るタイミングでのみ見られる潮の花」である
というものです。
ア
「波の花は」(中略)よく表現している⇒×
イ
これが正解です。
ウ
「満潮の波の様子」⇒×(満潮になっていくタイミングでの波の様子です。)
「新春のめでたさ」⇒×(無関係)
エ
「波の花」とする方が一般的⇒×(筆者はこちらを支持しているわけではない)
問4
「そのような効果」という指示語の具体化を問う問題です。
ここでは、
・「花」⇒春を含蓄する
・比喩的表現(潮の波頭を花に喩える)
の2つの表現の効果であると考えます。
ア
華やかな新春の雰囲気⇒×(「春」ではありますが「新春」つまりお正月ではないですね。)
イ
信じていたい気持ちを妨げる⇒×(疑うな、なので信じる気持ちを促しています)
ウ
〇
エ
日本人の感性を再確認⇒×(無関係)
問5
傍線部5付近のキーワードは「神仏の威徳」でしたね。
これをきちんと踏まえられている選択肢を選びましょう。
ア
「疑う余地のないこと」⇒×(疑う余地のないことであればわざわざ「疑うな」と言う必要はありません)
イ
「神仏の威徳」をわかりやすく示す⇒〇
ウ
「神仏のみが成し得る」⇒×(「のみ」とは書いてありません)
エ
「神仏の威徳」の存在は表現されていない⇒×
今回の解説は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。
また別の解説記事でお会いしましょう!
都立戸山高校に合格するなら自校作成専門対策塾 誠学会
都立戸山高校は自校作成問題を出す高校の中でも、制服もなく、上位を争う受験者数が多い人気校になります。内申点はオール5の生徒がほとんどを占め、ハイレベルな対策が必要になります。具体的な対策が知りたい方は、ぜひ誠学会にお問い合わせくださいませ。