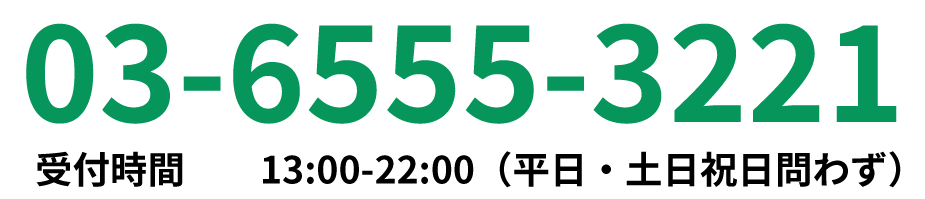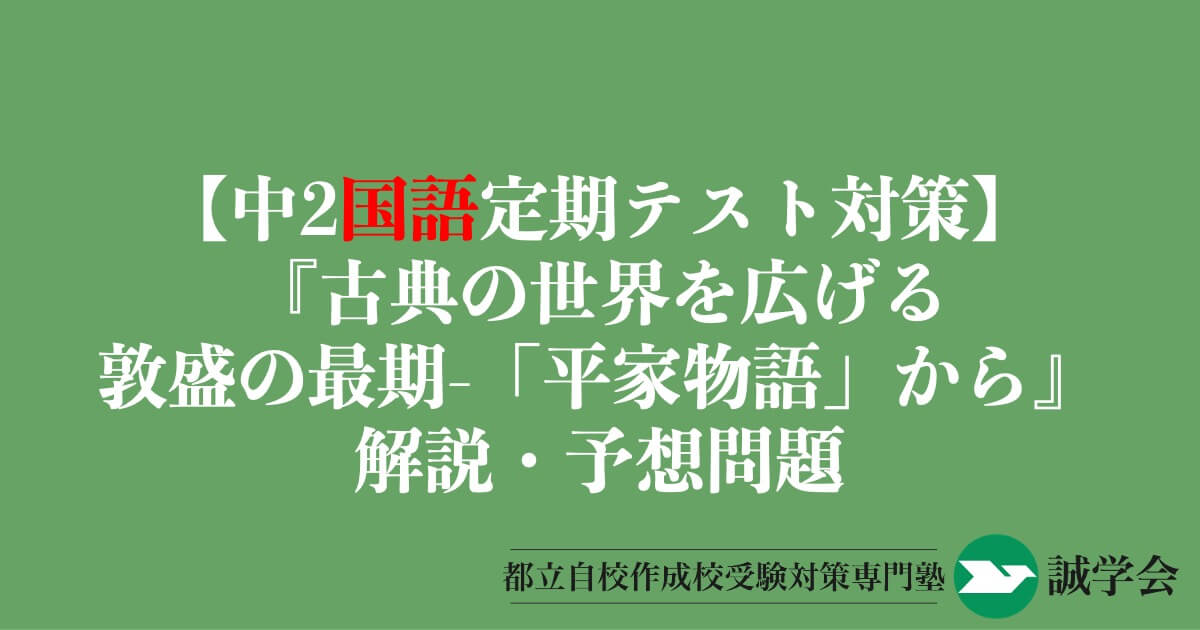こんにちは!都立自校作成校受験対策専門塾・誠学会の中山です。
この記事では、公立中学校の中学2年生の光村図書出版が出している国語の教科書の中の『古典の世界を広げる-敦盛の最期 「平家物語」から』の要点の解説と定期テストで出そうな問題の解説をします。
東京都の公立中学校で光村図書出版の国語の教科書を使っている方の定期テスト対策にお使いください。
※以下の地域に当てはまる方がこちらの教科書の対象です。
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、足立区、葛飾区、立川市、武蔵野市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、西東京市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、羽村市、あきる野市、西多摩地区、大島地区、八丈地区、小笠原村
では解説を始めます。
目次
- 1 『古典の世界を広げる-敦盛の最期 「平家物語」から』のあらすじ
- 2 『古典の世界を広げる-敦盛の最期 「平家物語」から』の定期テスト予想問題
- 2.1 Q. P285 9行目~P286 14行目までの本文の中には擬声語が一つ、擬態語が二つ用いられています。それぞれ古文の中から書き抜きなさい。
- 2.2 Q. P285 11行目の「見ければ」・・・①と、P285 12行目の「薄化粧して」・・・②は、それぞれ誰の動作だと考えられますか?①、②の動作主をそれぞれ古文中から書き抜きなさい。
- 2.3 Q. P285 13行目「いづくに刀を立つべしともおぼえず」とありますが、それはなぜだと考えられますか?30字程度で書きなさい。
- 2.4 Q. P286 6行目「汝がためにはよい敵ぞ」とありますが、「よい敵」とはどのような意味だと考えられますか?15字程度で書きなさい。
- 2.5 Q. P286 7行目「名乗らずとも顎を取って人に問へ。見知らうずるぞ」には、若武者のどのような気持ちが表れていると考えられますか?20字程度で書きなさい。
- 2.6 Q. P286 8行目「あつぱれ、大将軍や」とありますが、直実は若武者の何に感嘆していると考えられますか?25字程度で書きなさい。
- 2.7 Q. P286 13行目「あはれ助け奉らばや」とありますが、直実がこう思った理由を二つ書きなさい。それぞれ40字程度で書きなさい。
- 2.8 Q. P285 9行目~P286 14行目の本文から、直実の子供に対する態度に関してどのようなことが読み取れるでしょうか?20字程度で書きなさい。
- 2.9 Q. P287 1行目「仕り候はめ」・・・Aと、P287 16行目「よもあらじ」・・・Bとありますが、A,Bそれぞれの現代語訳を書きなさい。
- 2.10 Q. P286 15行目「助け参らせんとは存じ候へども」とありますが、直実はそれでもどうして若武者を討とうと決意したのですか?理由を45字程度で書きなさい。
- 2.11 Q. P286 16行目「同じくは」とありますが、具体的にはどういう意味だと考えらえますか?15字程度で本文の古文に続くように書きなさい。
- 2.12 Q, P287 4行目「いづくに刀を立つべしともおぼえず」とありますが、直実はなぜこのような状態になったと考えられますか?次の文の・・・に当てはまる言葉を現代語訳中から書き抜きなさい。
- 2.13 Q. P287 4行目「いづくに刀を立つべしともおぼえず」とありますが、直実のとまどう様子を端的に表していると考えられる言葉を古文中から四字で書き抜きなさい。
- 2.14 Q. P287 8行目「弓矢取る身ほど口惜しかりけるものはなし」に関して、なぜこのように思ったと考えられますか。次の文の①、②に当てはまる言葉を現代語訳中から抜き出して答えなさい。
- 2.15 Q. P287 8行目「弓矢取る身ほど口惜しかりけるものはなし」に関して、このような思いを味わった直実は、自らの今後をどう考えるようになったでしょうか。そのことがわかる言葉を古文中から九字で書き抜きなさい。
- 2.16 Q. P287 13行目「錦の袋に入れたる笛」とありますが、この笛を見たとき直実はどのような気持ちになったでしょうか。25字程度で書きなさい。
- 3 内申点対策・定期テスト対策なら自校作成校専門対策塾 誠学会
『古典の世界を広げる-敦盛の最期 「平家物語」から』のあらすじ
一の谷の戦いで総崩れになり退却する平家一門だったが、源氏の熊谷次郎直実が平家の敦盛見つけては一騎打ちをして手柄を立てようとしました。呼び止められた敦盛は、逃げればよかったものを「逃げれば平家一門の恥」と思い一騎打ちに応じ、結果、打ち取られてしまいました。少年を討ち取ったことを後悔した熊谷次郎直実は、武家をやめて出家することになったという物語です。
『古典の世界を広げる-敦盛の最期 「平家物語」から』の定期テスト予想問題
Q. P285 9行目~P286 14行目までの本文の中には擬声語が一つ、擬態語が二つ用いられています。それぞれ古文の中から書き抜きなさい。
A. 擬声語・・・どうど
擬態語・・・むずと、きつと
Q. P285 11行目の「見ければ」・・・①と、P285 12行目の「薄化粧して」・・・②は、それぞれ誰の動作だと考えられますか?①、②の動作主をそれぞれ古文中から書き抜きなさい。
A. ①熊谷次郎直実 ②大将軍(この殿)
Q. P285 13行目「いづくに刀を立つべしともおぼえず」とありますが、それはなぜだと考えられますか?30字程度で書きなさい。
A. 相手が、我が子ほどの年恰好の美しい顔をした若者だったから。
Q. P286 6行目「汝がためにはよい敵ぞ」とありますが、「よい敵」とはどのような意味だと考えられますか?15字程度で書きなさい。
A. 討ち取ったら大きな手柄になる敵。
Q. P286 7行目「名乗らずとも顎を取って人に問へ。見知らうずるぞ」には、若武者のどのような気持ちが表れていると考えられますか?20字程度で書きなさい。
A. 自分は名の知られた武者であるという自負。
Q. P286 8行目「あつぱれ、大将軍や」とありますが、直実は若武者の何に感嘆していると考えられますか?25字程度で書きなさい。
A. 死を前にしても誇りを失わず、堂々としている様子。
Q. P286 13行目「あはれ助け奉らばや」とありますが、直実がこう思った理由を二つ書きなさい。それぞれ40字程度で書きなさい。
A. 若武者の命を助けたところで合戦の勝ち負けが変わるわけではないと考えたから。
若武者が討たれたと聞いたなら、その父はきっとひどく嘆かれることだろうと考えたから。
(順不同)
Q. P285 9行目~P286 14行目の本文から、直実の子供に対する態度に関してどのようなことが読み取れるでしょうか?20字程度で書きなさい。
A. 子どもに対して深い愛情をもっている。
Q. P287 1行目「仕り候はめ」・・・Aと、P287 16行目「よもあらじ」・・・Bとありますが、A,Bそれぞれの現代語訳を書きなさい。
A. A・・・いたしましょう
B・・・決してあるまい
Q. P286 15行目「助け参らせんとは存じ候へども」とありますが、直実はそれでもどうして若武者を討とうと決意したのですか?理由を45字程度で書きなさい。
A. 背後から直実の味方の軍兵が大勢集まってきており、もう若武者は逃げられないと思ったから。
Q. P286 16行目「同じくは」とありますが、具体的にはどういう意味だと考えらえますか?15字程度で本文の古文に続くように書きなさい。
A.どちらにしろ討ち取れられるのならば。
Q, P287 4行目「いづくに刀を立つべしともおぼえず」とありますが、直実はなぜこのような状態になったと考えられますか?次の文の・・・に当てはまる言葉を現代語訳中から書き抜きなさい。
“若武者が・・・しかたなかったから。”
A.かわいそうで
Q. P287 4行目「いづくに刀を立つべしともおぼえず」とありますが、直実のとまどう様子を端的に表していると考えられる言葉を古文中から四字で書き抜きなさい。
A. 前後不覚
Q. P287 8行目「弓矢取る身ほど口惜しかりけるものはなし」に関して、なぜこのように思ったと考えられますか。次の文の①、②に当てはまる言葉を現代語訳中から抜き出して答えなさい。
“武芸の家に生まれていなければ、若武者を①(二字)にも討ち取るような②(四字)に遭うことはなかったから。
A. ①無情 ②つらいめ
Q. P287 8行目「弓矢取る身ほど口惜しかりけるものはなし」に関して、このような思いを味わった直実は、自らの今後をどう考えるようになったでしょうか。そのことがわかる言葉を古文中から九字で書き抜きなさい。
A. 発心の思は進みけれ
Q. P287 13行目「錦の袋に入れたる笛」とありますが、この笛を見たとき直実はどのような気持ちになったでしょうか。25字程度で書きなさい。
A. 若武者の優雅さに感じ入っていっそう哀れに思う気持ち。
内申点対策・定期テスト対策なら自校作成校専門対策塾 誠学会
都立高校の自校作成校(日比谷、西、戸山、青山、新宿、国立、立川、八王子東、国分寺、国際、墨田川)と言われるハイレベルな高校を目指す方は内申点をほぼオール5にしなければなりません。しかし、一般入試の対策もしなければならず、なかなか学校の定期テストの時間を費やせない方もいるはずです。
そのような方に一般入試対策だけでなく効率的な内申点対策も指導しております。具体的な対策が知りたい方は、ぜひ誠学会にお問い合わせくださいませ。