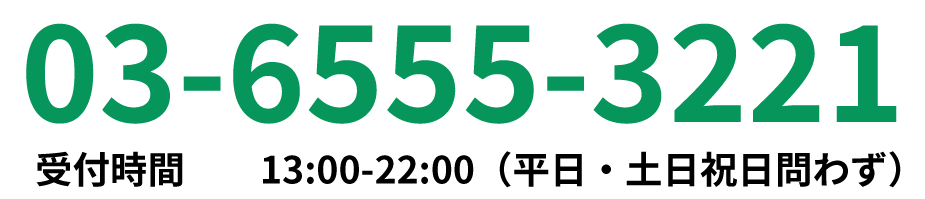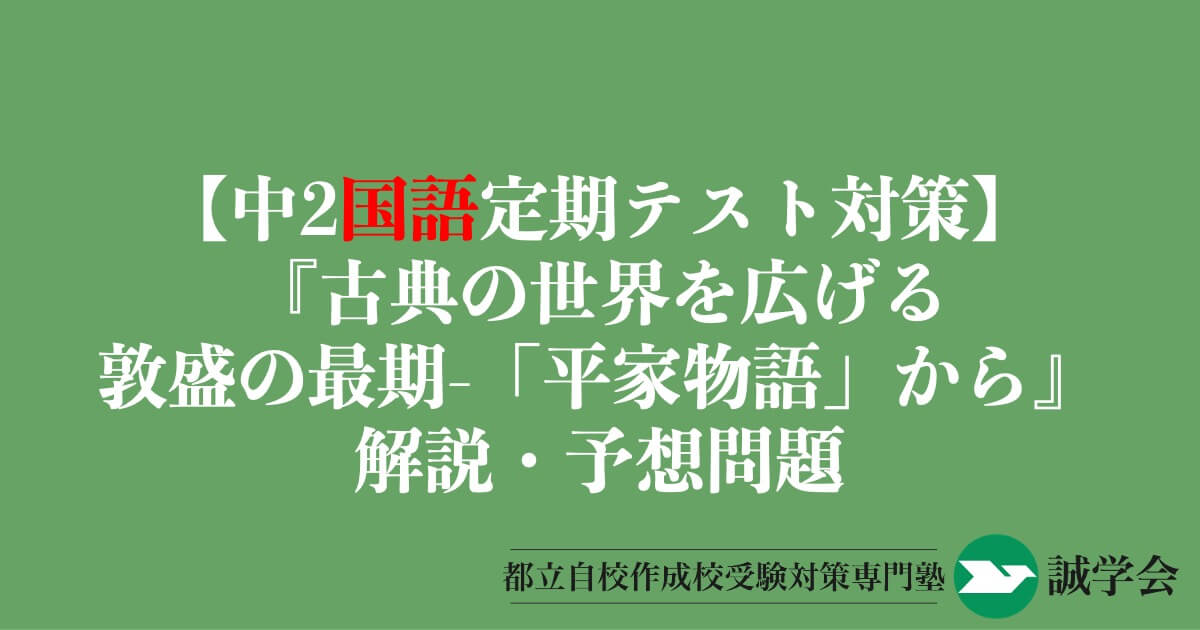こんにちは!都立自校作成校受験対策専門塾・誠学会の中山です。
この記事では、公立中学校の中学2年生の光村図書出版が出している国語の教科書の中の『生物が記録する科学 バイオロギングの可能性』の要点の解説と定期テストで出そうな問題の解説をします。
東京都の公立中学校で光村図書出版の国語の教科書を使っている方の定期テスト対策にお使いください。
※以下の地域に当てはまる方がこちらの教科書の対象です。
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、足立区、葛飾区、立川市、武蔵野市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、西東京市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、羽村市、あきる野市、西多摩地区、大島地区、八丈地区、小笠原村
では解説を始めます。
目次
- 1 『生物が記録する科学 バイオロギングの可能性』のあらすじ
- 2 『生物が記録する科学 バイオロギングの可能性』の定期テスト予想問題
- 2.1 Q.P279 上段 18行目「その答えが見えてきた」とありますが、見えてきた答えとはどういうものですか?それが書かれている一文を文中から探しなさい。その初めの5字を書き抜きましょう。
- 2.2 Q. P279 上段 18行目「その答えが見えてきた」とありますが、「その答え」は、どのような事実から引き出されたものだと考えられますか?
- 2.3 Q.P279 下段 17行目「データ」とありますが、何のデータですか?二つ挙げなさい。
- 2.4 Q.P279 下段 17行目「確かにペンギンたちは、ときどき深く潜るようになった」とありますが、それはなぜだと筆者は考えましたか?
- 2.5 Q.ワシントン岬にあるエンペラーペンギンの集団繁殖地での調査からわかったことは何か?
- 2.6 Q.筆者は、「バイオロギング」を用いたペンギンの調査を通してどのようなことに気づきましたか?それに関してまとめた次の文のA・Bに当てはまる言葉を、Aは四字、Bは八字で文中から書き抜きなさい。
- 2.7 Q. P281 上段 16行目「私たちは、群れの中の三羽に深度記録計を取り付けて調べてみた」とありますが、何を調べるために深度記録計をアデリーペンギンに取り付けたのだと考えられますか?次の文章の・・・に当てはまる言葉を文中から十六字で探して、その初めと終わりの五字を書き抜きなさい。
- 2.8 Q.P282の図3からわかったことに関してまとめた次の文章のC・Dに当てはまる言葉を書き抜きなさい。Cは八字、Dは五字で文中から書き抜きなさい。
- 2.9 Q.P282の図3から、三羽のペンギンが潜水の開始と終了を同時にして、異なる深さで餌を捕るという行動を取るのは何のためだと考えられますか?
- 2.10 Q.P282 下段 4行目「私たち研究者は、数々の失敗を重ねながら、この方法を開拓してきた」とありますが、「バイオロキング」という方法の開拓によって動物たちの調査はどう変わったと考えられますか?
- 2.11 Q.この本文が述べていることを要約しなさい。
- 3 内申点対策・定期テスト対策なら自校作成校専門対策塾 誠学会
『生物が記録する科学 バイオロギングの可能性』のあらすじ
筆者は佐藤克文であり、ウミガメやサメといった水生動物が、普段暮らしている水中でどのように活動しているか知るのは難しかったが、小型の記録計を動物に取りつけて海に放し、しばらく後でデータを分析するバイオロギングという方法が編み出された。それにより、エンペラーペンギンやアデリーペンギンの潜水行動が明らかになったことに関する説明文です。
『生物が記録する科学 バイオロギングの可能性』の定期テスト予想問題
Q.P279 上段 18行目「その答えが見えてきた」とありますが、見えてきた答えとはどういうものですか?それが書かれている一文を文中から探しなさい。その初めの5字を書き抜きましょう。
A.浅く潜って(P279 下段 5行目)
Q. P279 上段 18行目「その答えが見えてきた」とありますが、「その答え」は、どのような事実から引き出されたものだと考えられますか?
A.ペンギンは、氷の裏側のくぼみに潜む魚をついばんで食べていたという事実。
Q.P279 下段 17行目「データ」とありますが、何のデータですか?二つ挙げなさい。
A.潜水深度 潜水時間
Q.P279 下段 17行目「確かにペンギンたちは、ときどき深く潜るようになった」とありますが、それはなぜだと筆者は考えましたか?
“たくさんのペンギンがいると、・・・から。” の・・・に当てはまる言葉を文中から二十五字以内で書き抜きなさい。
A.浅い所にいる餌はすぐに捕り尽くされてしまう(P280 14行目)
Q.ワシントン岬にあるエンペラーペンギンの集団繁殖地での調査からわかったことは何か?
A.ペンギンが餌をより多く捕るためには、短い潜水を数多く繰り返した方が効率がよいということ。
Q.筆者は、「バイオロギング」を用いたペンギンの調査を通してどのようなことに気づきましたか?それに関してまとめた次の文のA・Bに当てはまる言葉を、Aは四字、Bは八字で文中から書き抜きなさい。
“野生動物にとって重要なのは、Aを発揮することではなく、Bことだということ。”
A. A・・・最大能力 B・・・効率よく餌を捕る
Q. P281 上段 16行目「私たちは、群れの中の三羽に深度記録計を取り付けて調べてみた」とありますが、何を調べるために深度記録計をアデリーペンギンに取り付けたのだと考えられますか?次の文章の・・・に当てはまる言葉を文中から十六字で探して、その初めと終わりの五字を書き抜きなさい。
“アデリーペンギンが・・・のかを観察するため”
A.水中でもい~捕っている(P281 上段 14行目)
Q.P282の図3からわかったことに関してまとめた次の文章のC・Dに当てはまる言葉を書き抜きなさい。Cは八字、Dは五字で文中から書き抜きなさい。
“三羽のペンギンは、Cを同時にして、Dで餌を捕っていること。
A. C・・・潜水の開始と終了 D・・・異なる深さ
Q.P282の図3から、三羽のペンギンが潜水の開始と終了を同時にして、異なる深さで餌を捕るという行動を取るのは何のためだと考えられますか?
次の文の1・2に当てはまる言葉を、1は二字、2は九字で文中から書き抜きなさい。
“水中への出入りを 1 に行うことで、2 ため。
A.1・・・一斉 2・・・捕食者から身を守る
Q.P282 下段 4行目「私たち研究者は、数々の失敗を重ねながら、この方法を開拓してきた」とありますが、「バイオロキング」という方法の開拓によって動物たちの調査はどう変わったと考えられますか?
A.人間の行動圏より広い、さまざまな環境で生きる動物たちのデータを集められるようになった。
Q.この本文が述べていることを要約しなさい。
A.ペンギンの餌捕りを「バイオロキング」による野生動物の調査の具体例として挙げ、データから未知の世界を施行することの大切さを述べている。
以上で『生物が記録する科学 バイオロギングの可能性』の解説と予想問題を終わります。しっかり予想問題を解いて、定期テストで高得点をとりましょう!
内申点対策・定期テスト対策なら自校作成校専門対策塾 誠学会
都立高校の自校作成校(日比谷、西、戸山、青山、新宿、国立、立川、八王子東、国分寺、国際、墨田川)と言われるハイレベルな高校を目指す方は内申点をほぼオール5にしなければなりません。しかし、一般入試の対策もしなければならず、なかなか学校の定期テストの時間を費やせない方もいるはずです。
そのような方に一般入試対策だけでなく効率的な内申点対策も指導しております。具体的な対策が知りたい方は、ぜひ誠学会にお問い合わせくださいませ。